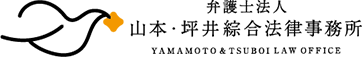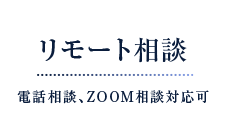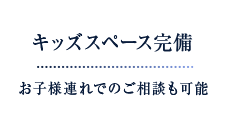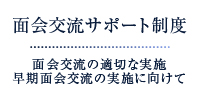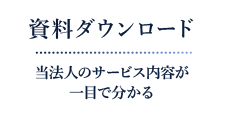弁護士ブログ
2024/06/20
相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
両親や親族などが亡くなって,種々の手続等にお困りの方も多いかと思います。
何かしないといけないとは分っていても,なかなか手を付けられずにいることの一つが「不動産」だと思います。
まず,不動産を相続する際の不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
この相続登記が2024(令和6)年4月1日から義務化されました。
相続登記をしないまま放置しておくと不動産の所有者が分からなくなり,土地や建物の売買・活用ができないなど,将来的に様々なトラブルが発生する可能性があります。
これらのトラブルを回避するために必要となるのが「相続登記」になります。
今までは,この相続登記をいつまでにしないといけないなどの定めはありませんでした。
なので,相続登記が必要なことを知らなかったり,費用がかかるので放置していたり,そもそも誰が相続するのか分からない等々の理由で相続登記をしてなくても罰則はありませんでした。そのため,相続人が相続登記を行わなくても殆どデメリットを感じませんでした。
しかし,近年「空き家」や「空き地」が社会問題となっており,この解消に向けて「相続登記」が義務化されました。
2024(令和6)年4月1日から施行された不動産登記法改正後は
① 相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をする。
② 相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合,10万円以下の過料が課せられます。
③ また「住所変更登記の義務化」も行われますので,不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が課せられます。
注意しなければならないのは,過去の相続分(2024(令和6)年4月1日以前に相続した不動産)にも相続登記義務が課せられるという点です。なので,過去の相続分は改正法の施行日(2024(令和6)年4月1日)から3年以内に相続登記をしなければ罰則を科せられる可能性があるということです。
相続登記が義務化されることで,所有者はその相続した不動産の処分や活用ができるようになりますが
例えば,相続人の共有名義にした場合,
相続人の中に,ローンや借金をしている方が含まれているかもそれません。その場合,債権者である相続人が法定相続による相続登記を申請すると,相続人の持ち分を差し押さえることができます。
また持ち分を売却したり担保として使用したりもできます。その結果,第三者が権利を主張する等のトラブルがある場合もあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,相続に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。
その他,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。
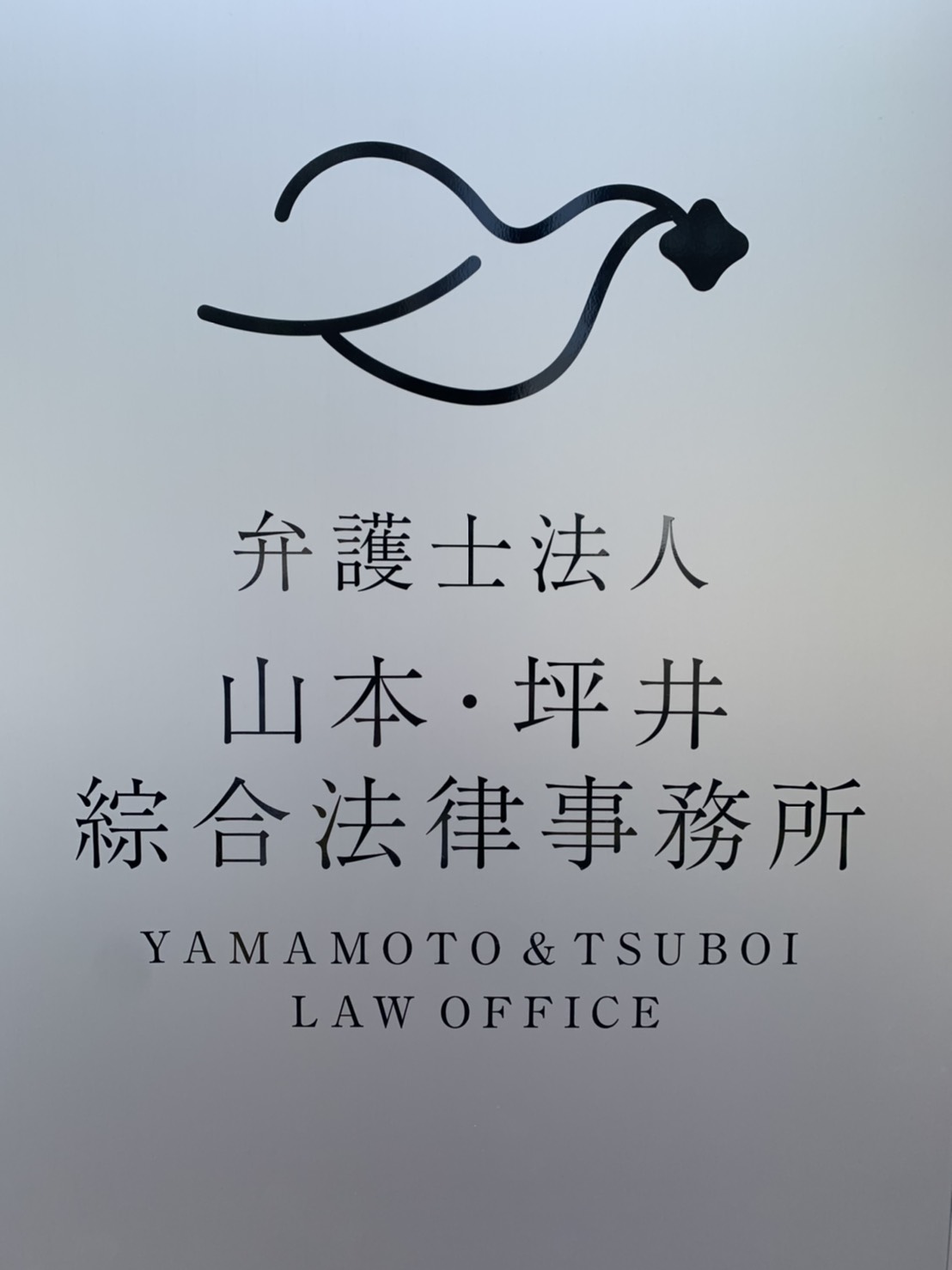
弁護士ブログ
2024/06/13
刑事事件の面会土日祝日行います!!

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。
当事務所福岡オフィスでは、開業以来、日々多くの刑事事件のご相談、ご依頼をお受けしております。
福岡県内だけでなく、九州地区全域、西日本全域で刑事事件の弁護のご依頼をお受けしております。
全国各地どこへでも面会に行きます!!刑事事件は早期の面会が重要です!
早期面会により被疑者の取り調べの対応へのアドバイス、勾留却下を含む早期の身体拘束からの解放への手続き、
身体拘束中の被疑者の不安を解消することなど、非常に重要な役割があります。
当事務所福岡オフィスでは、長崎オフィス、香川オフィスと連携を図り、西日本を中心に全国どこでも早期面会を実施しております。
また、当事務所福岡オフィスでは、電話での法律相談やZOOMでの法律相談を実施しているため、遠方でもまずは相談を行うことができます。
刑事事件に関するご相談はどのようなご相談でも相談料無料のため、安心してご相談していただけます。
電話による相談も初回相談料無料の法律事務所は、数が多くありません。特に、土日祝日対応している法律事務所は極めて少ないと思います。
しかし、逮捕は土日祝日関係なく実施されます。旅行先でのトラブルなども少なくありません。
当事務所福岡オフィスの弁護士は土日祝日でも被疑者の面会に早期に対応いたします。
性犯罪、暴行事件、詐欺事件、窃盗事件等、様々な刑事事件を対応してきたノウハウがあります。
逮捕された方だけでなく、在宅事件でお悩みの方、在宅事件では国選弁護人をつけることができません。
是非、一度初回相談料無料、土日祝日対応している当事務所福岡オフィスの弁護士までご相談ください!!
刑事事件の弁護士に悩んだら当事務所福岡オフィスにお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士坪井智之

弁護士ブログ
2024/06/13
撮影罪について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、撮影罪に関するご相談・ご依頼も多数お受けしています。
令和5年7月、撮影罪を規定する性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)が施行されました。
撮影罪とは、「性的姿態等撮影罪」の略称で、身体の性的な部位や下着等を相手の同意なく撮影したり盗撮したりする罪のことです。
令和5年7月以前の盗撮に関しては、各都道府県の迷惑行為防止条例で処罰されていましたが、地域によって罰則や処罰の範囲が違ったり、近年のスマートフォンの普及により年々盗撮件数が増えてきていたりしていることから撮影罪が新設され、全国一律で処罰できるようになりました。
毎年、夏が近づくと、薄着や露出が増えることから、盗撮に関するご相談が増加します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、警察や検察を通して被害者へ早急に連絡をとり、示談できるよう速やかに対応します。
もし、警察に逮捕された場合や逮捕されないか不安要素がある場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士ブログ
2024/04/24
ゴールデンウィーク中の営業について
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談者様に限り、通常の土日祝日と同様、ご相談のご予約をお受けしております。
ゴールデンウィークに旅行にいかれる方も多いと思いますが、旅行先でトラブルに巻き込まれる方や、はめを外しすぎて、刑事事件を起こしてしまう方も多数います。
しかし、ゴールデンウィーク中、弁護士事務所は、お休みのところが多く、困った時に弁護士に相談できないことがあります。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談に即日対応いたしますので、万一、刑事事件や離婚問題、不貞問題、相続や交通事故などのお悩みが生じた場合でもご安心ください。
当事務所の弁護士があなたのお悩みを解消致します。
ゴールデンウィーク中弁護士に困ったら、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお気軽にお電話ください。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之

弁護士ブログ
2024/03/21
LGBTQ+について
先日,神奈川県相模原の相模原青年会議所主催の講演に参加してきました。「乗り遅れるな!Ⅾ&Iの新時代経営」とのタイトルでLGBTQ+の方を経営者目線で見た場合,今後人を採用していくことについて,学ぶことができました。
そもそも,皆様は,LGBTQ+の意味やD&Iの言葉の意味をご存じでしょうか?
Lは「Lesbian」,Gは「Gay」,Bは「Bisexual」,Tは「Trans-gender」,Qは「Questioning,性的指向を決められない」+は「その他を指し,具体的には,自身を男性とも女性とも認識しない人,多くのジェンダーひかれる人,性別に関係なくひかれる人。また,他人への性的魅力をほとんどあるいはまったく感じない人など」をいいます。
そして,Ⅾ&Itoとは,Dは,ダイバーシティ,多様性を意味し,Iは,インクルージョン,受け入れることを意味する。これらを合わせて,「ダイバーシティ&インクルージョン」とは,多様性を認識するだけでなく,一人ひとりが受け入れ,尊重することによって個人の力が発揮できる環境を整備委したり,働きかけたりしていくという考え方です。
昨今,LGBTQ+に含まれる方の割合は,人口の約10%弱と言われており,約10人に一人がLGBTQ+に該当することになります。
身近にいる10人の方を思い浮かべてください,実はその方の一人はLGBTQ+に含まれることになります。皆様,思い浮かぶ方はいますでしょうか?実際には,そんなにいるのって思う方が多いのではないでしょうか?
周囲には,LGBTQ+の方がこれだけ多数をおり,普段何気ない会話の中で人を傷つけているかもしれません。これは会社でも同じです。男性トイレ,女性トイレ兼用でない場合,どちらを利用すべきか悩んでいる社員がいるかもしれませんし,会社内での恋愛の話になると知らずに傷つけていることがあるかもしれません。
このように会社内だけみても今後しっかり環境整備を整えていく必要があることは明らかであります。
多様な人財が輝く会社こそ成長・発展していく会社であるということを今回講演を受け,改めて認識を受けました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所においても,多様なクライアントの要望や悩みに寄り添えることができるように,多様な人財が輝く法律事務所を目指していきたいと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
New Entry
Archive
- 2024 / 06
- 2024 / 04
- 2024 / 03
- 2023 / 12
- 2023 / 11
- 2023 / 10
- 2023 / 09
- 2023 / 08
- 2023 / 07
- 2023 / 06
- 2023 / 05
- 2023 / 04
- 2023 / 03
- 2023 / 01
- 2022 / 12
- 2022 / 09
- 2022 / 08
- 2022 / 07
- 2022 / 06
- 2022 / 05
- 2022 / 04
- 2022 / 02
- 2022 / 01
- 2021 / 12
- 2021 / 11
- 2021 / 10
- 2021 / 09
- 2021 / 08
- 2021 / 07
- 2021 / 06
- 2021 / 05
- 2021 / 04