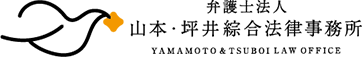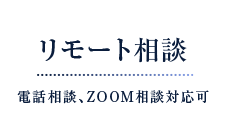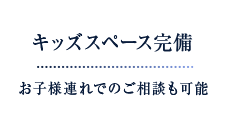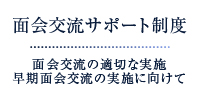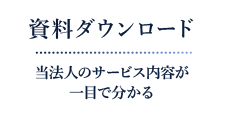弁護士ブログ
2022/05/23
電子計算機使用詐欺罪について
今話題になっている「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)ですが、テレビ報道を通じて初めて聞いた方もいらっしゃるのではないかと思います。本稿では、同罪について皆様に知っていただければと思います。
電子計算機器使用詐欺罪は、刑法246条の2に「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する」と規定されています。なお、「前条」とは刑法246条の詐欺罪を言います。「電子計算機」と難しい表現がされていますが、これはパソコンと思っていただけると想像しやすいかと思います。つまり、すごく簡単にいうと、「人」ではなく、「パソコン」を介した詐欺罪が、本罪にあたります。
刑法246条の2は、前段の(1)機械に嘘を入力して経済的な価値のある記録を作り不正な利益を得た罪と、後段の(2)機械に虚偽の情報を提供することによって不正な利益を得た罪の2つに分けられます。
(1)は、銀行の管理するデータバンクを不正にいじって自己の口座に不正にお金を流入させたような事案があたります。一方(2)は、自己の口座内に誤振込があり、そのお金が自己の資産でないことを把握しつつも、自己の資産であると装い機械を操作し、ご振り込みされた金銭を引き出すような事案があたります。
(1)の場合と異なり、(2)の場合には、自分の口座内のお金が増えているうれしさから、自分のお金ではないと分かりつつも、ついつい引き出して使用してしまう気持ちも分からなくはないですが、そのようなことをしてしまうと「電子計算機使用詐欺罪」が成立してしまうのです。
自分の口座に見覚えのないお金が振り込まれている場合には、慎重な法的判断が必要になってきますので、一度山本・坪井綜合法律事務所にお問い合わせください。山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件を多く扱っており、また土日祝日も対応可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 川岸司佳
弁護士ブログ
2022/05/23
生活保護受給者の破産について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、日々は破産の相談を受けます。破産は、多額の借金のために首が回らない方にとって、人生をやり直すきっかけになります。「破産したら人生の終わりだ」という言葉を聞くこともありますが、これは全く逆なのです。
また、多額の債務をかかえて相談に来られる方の中には、自身が生活保護受給者であることを理由に、「破産はできないのではないか」と元より破産を諦めている方もいらっしゃいます。
しかし、生活保護受給者であっても、破産は当然認められます。
確かに、生活保護受給者ということで、生活保護受給者であるにもかかわらず、給付額以上の借り入れがどうして必要になってしまったのか、という理由は破産を申し立てるときに説明しないといけませんが、破産が全く認められないということはありません。
また、生活保護受給者の場合、給与所得者に比べ収入が低いことが多く、債務額が100万円に達しない状態で破産をすることも十分あり得ます。
債務の取立てに悩んでいるのであれば、一度山本・坪井綜合法律事務所にお問い合わせください。山本・坪井綜合法律事務所では、破産事件を多く扱っており、また土日祝日も対応可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 川岸司佳
弁護士ブログ
2022/05/20
法律用語について(相続関連)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは,日々様々な法律相談をお受けしております。
その中でよく耳にするのが,『専門的な知識がないからよくわからない。』,『聞いたこともないことを言われて理解できない。』ということです。
そのため,今回のブログではよく耳にするけれど,なんとなく理解していることの多い相続に関する法律用語について簡単に説明いたします。
【遺留分(いりゅうぶん)】
遺留分とは,被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証される相続財産の割合のことです。
遺留分は,被相続人の直系卑属・直系尊属と配偶者にだけ認められるため,被相続人の兄弟姉妹には存在しません。
相続が始まる前に,被相続人の子もしくは被相続人の兄弟姉妹が死亡している,または相続欠格・排除によって相続権を失っている場合には,その子が代わりに相続する代襲相続人にも遺留分は認められます。
【生前贈与(せいぜんぞうよ)】
生前贈与とは,亡くなる前に,自分の財産を分け与えることを言います。
自分が生きてるうちに特定の人に財産を贈与しておくことで,例えば関係がこじれている状況の親族に対し,自分の財産を相続させることを防ぐことができます。
ただ,何の手続きもせずに生前贈与を行った場合は,相続税よりも贈与税が高くなることがあるため注意が必要です。
【遺産分割(いさんぶんかつ)】
相続人が複数人いる場合に,遺産について相続人の間で遺産を分配することを言います。
【法定相続分】
遺言による遺産の配分指定がない場合に,民法の規定に従い各法定相続人が相続する遺産割合のことです。
上記のように,身近な問題である相続のことについても,よく耳にはするけど詳しい意味が分からない,また自分が理解してたことと認識が違うということも少なくありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは,専門家である弁護士が,わかりにくい法律用語や制度についてもしっかり説明し,ご相談いただいた方が少しでも理解しやすくお話をするよう心がけております。
ご相談だけでも,問題解決の糸口が見つかることがあります。
どのようなお悩みも,まずはお気軽にご相談ください。
一人で悩まず,あらたな第一歩を,わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 事務局
弁護士ブログ
2022/05/18
法定相続人について
相続では、民法上、相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といい、法定相続人は、配偶者と血族の2種類に分けられます。
配偶者は常に相続人となりますが、血族には順位がついており、先順位の者が相続人となります。
血族の相続順位は以下となっています。
第1順位…被相続人の子
子が死亡しているときは、その代襲者(子、孫、ひ孫等)
第2順位…直系尊属(被相続人の親等)
第3順位…被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡しているときは、その代襲者(子のみに限られ、孫、ひ孫等は含まれません)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、相続に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
相続に関することでお悩みの方は是非一度、福岡オフィスまでご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
事務局
弁護士ブログ
2022/05/17
離婚事件の取り組みについて パート7
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,監護者についてご説明します。
夫婦が別居した場合,夫婦のどちらが監護者になるかが定まらない場合,子にとって不利益が生じるおそれがあります。そこで,夫婦間で監護者の合意が成立しない場合に監護者の指定を求める審判により,監護者を定めることになります。
もっとも,別居中に監護者の指定により監護者が定まったとしても,婚姻中は夫婦の両方に親権があるため,監護権も夫婦両方に帰属していることになります。
子の監護者指定の審判において監護者を指定する基準として,一般的には子の利益の観点から判断されることになりますが,監護者を指定する場合にどのような事情が考慮されるのかについての判断はなかなか難しいところがありますので,弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
監護者に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志
New Entry
Archive
- 2025 / 10
- 2025 / 08
- 2025 / 06
- 2025 / 05
- 2025 / 03
- 2025 / 01
- 2024 / 12
- 2024 / 10
- 2024 / 06
- 2024 / 04
- 2024 / 03
- 2023 / 12
- 2023 / 11
- 2023 / 10
- 2023 / 09
- 2023 / 08
- 2023 / 07
- 2023 / 06
- 2023 / 05
- 2023 / 04
- 2023 / 03
- 2023 / 01
- 2022 / 12
- 2022 / 09
- 2022 / 08
- 2022 / 07
- 2022 / 06
- 2022 / 05
- 2022 / 04
- 2022 / 02
- 2022 / 01
- 2021 / 12
- 2021 / 11
- 2021 / 10
- 2021 / 09
- 2021 / 08
- 2021 / 07
- 2021 / 06
- 2021 / 05
- 2021 / 04