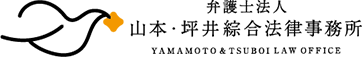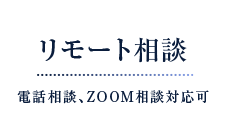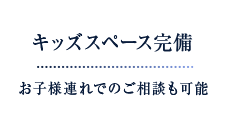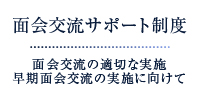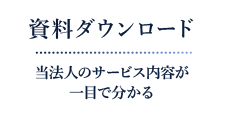弁護士ブログ
2023/08/23
訴状が届いた時
今回は訴状が届いた時の対応についてご紹介いたします。
訴状が届いた場合、まずは冷静になってください。
訴状は法的な通知であり、真剣に取り扱う必要があります。以下の手順を参考にして対応してください。
1. 訴状を注意深く読みましょう:訴状には、原告の主張や訴訟の根拠、要求事項などが記載されています。内容を理解するために時間をかけて読み込んでください。
2. 記録を整理しましょう:訴状に対する回答のために、関連する書類や証拠を整理しておくと役立ちます。重要な記録や証拠を見つけた場合は、それらを保管しておきましょう。
重要なことは、訴状に対して真剣に向き合い、必要な手続きを遵守することです。
弁護士の助けを借りることで、より適切な回答を行うことができます。
訴訟の内容に納得がいかない場合や、自分で回答することが難しい場合。訴訟の流れが分からない場合は、弁護士に相談しましょう。訴状に対する適切な回答をするためには、弁護士の助言を受けることが重要です。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所では、初回無料でご相談をお受けしております。
不安な気持ちが少しでも和らげるよう全力でサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士ブログ
2023/08/23
不同意性交等罪とは

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っております。
令和5年7月13日より「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が統合され、新たに「不同意性交等罪(刑法177条)」が創設されました。
施行前は「暴行や脅迫」により、被害者の抵抗が「著しく困難」な状況下で性交等に及んだ場合でなければ犯罪として処罰されませんでしたが、施行後は「同意がない性行為」が犯罪になり得ることが明確になりました。
被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。
性的行為について自ら判断できるとみなす「性交同意年齢」が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満への性交等も処罰対象となります。
不同意性交等罪は、夫婦間であっても適用されます。
不同意性交等罪をはじめ、刑事事件についてお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料でお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士ブログ
2023/08/23
詐欺罪について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、詐欺をはじめ刑事事件についてのご相談、お問い合わせを多く頂きます。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為のことをいいます。(刑法第246条)
他人から金銭を騙し取る以外にも、無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けることや、債務を不法に免れるなどすることも詐欺罪に該当します。
刑事事件は早期に対応をするかどうかで結果が大きく変わります。
逮捕後すぐに弁護士を入れれば、示談交渉や、身体拘束解放や不起訴処分に向けて動くことが可能となります。
対応が遅れると不利になることも多いため、刑事事件でご自身又はご家族が逮捕されたという方はすぐにご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料となっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士ブログ
2023/08/22
16歳未満の者に対する面会要求等の罪
16歳未満の子どもに対して、以下の行為をした場合、面会要求等の罪が成立することになりました。なお、相手方が13歳以上16歳未満の子どもであるとき(※)は、行為者が5歳以上年長である場合に限られます。
1⃣ わいせつ目的で、
① 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること
② 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること
③ 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2⃣ 1⃣の結果、わいせつ目的で会うこと
3⃣ 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求すること
※【相手方が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合に限られた理由】
一般的に、性犯罪の要素は「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」であると考えられているため、そのような自由な意思決定の前提となる能力が十分に備わっていない人に対しては、性的行為をしただけでその性的自由を侵害したと考えられます。
しかし、性的行為についての自由な意思決定のためには、上記能力だけではなく、行為の相手との関係でその行為が自分に与える影響について自律的に考えたり、その相手に対処する能力も必要であると考えられます。13歳以上16歳未満の年齢層は行為の性的意味を認識する能力が一律にないわけではないものの、行為の相手との関係では対処できない場合もあります。そのため、一般的に相手との年齢差が大きくなればなるほど、社会経験等の差によって対等性が失われていくことに鑑みて、13歳以上16歳未満の人との関係では絶対に対等な関係はあり得ないといえるような年長者による性的行為を一律に処罰対象とするため、心理学的・精神医学的知見も踏まえ、5歳以上年長の者による性的行為を処罰することとされたものです(法務省解説参照)。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
支店長弁護士 牟田 功一

弁護士ブログ
2023/08/22
離婚時のマイホーム問題
夫婦が離婚する際、財産分与や養育費などの問題がありますが、特にマイホームのことで悩まれている方が多くおられます。
マイホームの名義には、家の所有名義と住宅ローン名義があります。
特に、購入したマイホームのローン残高で、「住宅ローンが残っているが誰が払うのか」、「離婚してもマイホームに住み続けられるのか」、「共同名義になっているがどうしたらよいか」などといったマイホームに関する相談を多くお受けしています。
離婚の際のマイホームの対処方法について、ご説明します。
1 マイホームを売却する場合
離婚する際、購入したマイホームをどうするかが大きな問題です。
マイホームのローンが残っていない場合は、マイホームは売却し、そのお金を財産分与として、夫婦で分け合うことができます。しかし、マイホームのローンが残っている場合は、マイホームの査定金額とローン残高が問題となります。
〇 オーバーローンの場合
オーバーローンとは、住宅の査定金額よりローン残高の方が上回っている場合です。この場合、夫婦の片方が住み続けてローンを支払って行くのが一般的です。どうしても売却せざるを得ない場合は、残ったローンの支払いをどうするか、検討の必要があります。
住宅ローンを一括返済する場合は、まとまった資金が必要となります。資金がない場合は、一括返済が難しくなりますので、預貯金等や両親等の援助を受けることも必要かもしれません。残ったローンを一括返済できない場合は、不動産には「抵当権」という担保が付いているので、金融機関等の債権者の承諾を得ないと不動産を売却することはできません。「任意売却」と言って、金融機関等の債権者の許可を得て、住宅を売却する方法もあります。「任意売却」でも、残債務の支払い義務は逃れられませんので、注意が必要です。
〇 アンダーローンの場合
アンダーローンとは、住宅の査定金額よりローン残高が少ない場合です。ローン残高の方が少ないことから、マイホームを売却することでローンの全額返済も可能となり、もし残ったお金があれば、そのお金を夫婦で分け合うことができます。もし、住宅を売却しないのであれば、住宅ローンの名義を誰にして、誰がローンを支払っていくのか、住宅の所有名義を誰にするか、等多くの問題が発生します。
離婚で家を売却することが決定している場合は、家がいくらで売れるのか、数社の不動産会社に査定を依頼してみてください。
2 マイホームに住み続ける場合
離婚後、マイホームに住宅ローンの名義人が住み続ける場合と住宅ローンの名義人以外の者が住み続ける場合があります。
⑴ 住宅の名義人が住み続ける場合
マイホームを購入した時にローンを組んだ名義人がそのまま住宅に住み続ける場合は、住宅ローンの返済義務はローンを組んだ名義人にあることから、そのままローンを支払い続けることで、問題ないと思われます。しかし、離婚して家を出た配偶者が「連帯保証人」や「連帯債務者」となっている場合は、注意が必要です。
〇 住宅ローンが残っていない場合
住宅ローンが残っていない場合は、住宅を売却しなくても、財産分与として、その住宅の査定金額の半分を相手に支払うこととで、住宅の名義人が住み続けることができます。
〇 住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っているが、住宅の査定金額がローン残高より大きい場合は、プラスの財産として財産分与の対象となり、住宅を売却しなくても、住宅の査定金額からローン残高を差し引いた金額の
半分を相手に支払うこととなります。さらに、住宅を購入の際、配偶者の個人財産を頭金等として、一部支払っている場合は、それも財産分与として考慮される場合もあります。
〇 家を出た配偶者が「連帯保証人」や「連帯債務者」になっている場合
例えば、夫がローンの名義人で、家を出た妻が連帯保証人や連帯債務者となっている場合は、夫婦間で夫が支払うとの合意があっても、妻には金融機関への債権の責任は免れません。基本的に、連帯保証人などから外れることは難しいです。もし、元夫が住宅ローンの支払いを滞納した場合、家を出ている元妻が住宅ローンの支払いをしなくてはならなくなります。離婚の話し合いの時、連帯保証などについて、家を出た妻の不利益にならないように元夫が住宅ローンを滞納した場合の対応を明確にしたうえで、公正証書としておくことも、予防策の一つです。
⑵ 住宅の名義人以外の者が住み続ける場合
マイホームを購入した時の家の名義人であり、かつ住宅ローンを組んだ名義人が家を出て、名義人以外の配偶者などがそのまま住宅に住み続ける場合は、色々な問題があります。例えば、住宅の名義人で、かつ住宅ローンの名義人の夫が家を出て、妻と子供がそのまま住宅に住み続ける場合として、お話しします。
〇 住宅ローンが残っていない場合
住宅ローンが残っていない場合は、住宅を売却しないで、妻と子供が住み続けることもできます。そういった場合は、財産分与や養育費などに影響することがありますので、離婚前に相手とよく話し合う必要があります。また、妻と子供が家に住み続け、妻が家を取得する場合は、家の名義を夫のままにしておくと、夫の財産として扱われることになりますので、名義変更が必要となります。
〇 住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている場合は、住宅の査定金額とローン残高が問題となります。
□ アンダーローンの場合
住宅の査定金額よりローン残高が少ない場合は、プラスの財産となりますので、財産分与の対象となります。
妻が住宅を取得し住み続けるならば、妻から夫へ財産分与の支払いが必要となりますが、
他の財産分与や養育費等が関係してくることから、離婚前に相手とよく話し合う必要があります。
□ オーバーローンの場合
住宅の査定金額よりローン残高の方が上回っている場合、基本的に住宅に住み続けるのならば、住宅ローンの名義人が離婚後もローン返済を続けなければなりません。住宅ローンの名義人以外の者(妻と子供)が住み続けるなら、ローンの名義変更と借り換えが必要となります。
住宅ローンの借り換えには、現在、借りている金融機関とは違う金融機関で、新たに借りることになります。このとき、夫あるいは妻のどちらかの単独名義にすることになりますが、金融機関の審査を通過しなければならず、名義人となる方の収入や返済能力によっては、ローンを組むのが難しくなる場合もありますので、金融機関に相談してください。 専業主婦など定期収入がない場合には、借り換えは難しいと考えられます。
また、住宅ローンの名義変更や借り換えをせず、ローンの名義人以外の者(妻と子供)が住み続けるのは、トラブルの原因となります。例えば、住宅の名義人の夫が勝手に住宅を売却したり、金融機関から一括返済を求められる可能性もあります。
3 共同名義となっている場合
最近では、夫婦が共働きをしていることから、マイホームも共同名義としている夫婦が増加しています。離婚に伴い、住宅の所有名義だけを夫又は妻の単独名義に変更する場合は、
金融機関の承諾が得られれば、名義変更は可能です。しかし、住宅ローンが夫婦共同名義となっている場合は、夫婦で「連帯債務」・「連帯保証」となっている場合があり、たとえ離婚したとしても、ローンを返済し続ける必要があります。もしも、離婚した後、元夫あるいは元妻の返済が滞ったとしたら、どちらかに債務が集中するかもしれません。そのため、離婚することになれば、住宅ローンの共同名義を解消する必要があります。住宅ローンの共同名義を解消する方法としては、「住宅ローンの借り換え」、「一括返済」、「家の売却」などが考えられます。
離婚前に、マイホームの問題について、配偶者としっかり話し合いを行い、取り決めてお
くことが必要です。
また、口頭だけで合意していても、後で守られないこともありますので、合意内容を公正証書にまとめておくことも必要かもしれません。
離婚に際して、マイホーム問題や財産分与、親権、養育費等について、後悔しないためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律福岡オフィスは、離婚や刑事事件をメインとした法律事務所で、相談件数や解決事案も多数あり、経験豊富な弁護士が在籍しております。離婚問題等でお悩みの方は、まず、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡してください。

New Entry
Archive
- 2025 / 10
- 2025 / 08
- 2025 / 06
- 2025 / 05
- 2025 / 03
- 2025 / 01
- 2024 / 12
- 2024 / 10
- 2024 / 06
- 2024 / 04
- 2024 / 03
- 2023 / 12
- 2023 / 11
- 2023 / 10
- 2023 / 09
- 2023 / 08
- 2023 / 07
- 2023 / 06
- 2023 / 05
- 2023 / 04
- 2023 / 03
- 2023 / 01
- 2022 / 12
- 2022 / 09
- 2022 / 08
- 2022 / 07
- 2022 / 06
- 2022 / 05
- 2022 / 04
- 2022 / 02
- 2022 / 01
- 2021 / 12
- 2021 / 11
- 2021 / 10
- 2021 / 09
- 2021 / 08
- 2021 / 07
- 2021 / 06
- 2021 / 05
- 2021 / 04